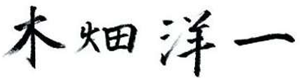東大駒場友の会は、2004年に、東京大学駒場キャンパスの教育研究活動の発展と福利厚生の向上をはかり、
大学が教育研究を通して地域と社会の発展に貢献することを目的に設立されました。
当会の活動に興味ご関心をお持ちの方、入会ご検討中の方は、こちらから
当会の行う教育、研究、文化活動に興味関心をお持ちで、当会設立の趣旨にご賛同いただける方は
東大関係者に関わらずどなたでも入会いただける開かれた会です(会友会員としてご入会ください)
2004年3月、東大駒場友の会の前身である「駒場友の会」は、東京大学駒場キャンパスの教育研究活動の発展と福利厚生の向上を図り、大学が教育研究を通して地域と社会の発展に貢献することを目的に設立されました。
会報やWEBサイトでの情報発信やイベントの開催を通じ、卒業生・学生やそのご家族・大学の間の交流を図り、教養学部、大学院総合文化研究科、大学院数理科学研究科の事業への協力と支援を行ってきました。2016年度の駒場友の会総会決議により、同年10月3日に一般社団法人「東大駒場友の会」として認められ法人化し、組織・財政基盤を整え、順調に活動を続けています。
新入生保護者を迎えての学部長との懇談会や研究者や卒業生を招いての講演会の開催、学内で行われる演奏会や駒場博物館展覧会への協力、学生向けの食育プログラムを推進しています。法人化後は、教養学部や学生団体の活動等への寄付事業に積極的に取り組み、学術・文化・スポーツを通じ多様性・国際性を涵養するプログラムへの支援、駒場図書館への図書の寄贈、さらにはキャンパスの環境整備への協力も行っています。
当会の活動趣旨にご賛同いただいた多数の終身会員・通常会員(卒業生・現役の教職員とOB・OGなど)と会友会員(学生の保護者・一般の方)の皆様からのご寄付を有効な支援に繋ぐため、教養学部とより一層の協力を図り、当会事業の発展に努めております。各種イベントへのご参加や寄付へのご協力を通じて駒場キャンパスをより一層身近に感じていただき、ともに親しく集いながらキャンパスでの教育研究活動および教養の発展と普及に寄与できたらと考えています。皆様のご入会をおまちしております。